人生で本当に驚いたことがいくつかありますが、なかでも「網膜には180度ひっくり返った倒立像が映っている」と知った時の衝撃は、いまも忘れられません。望遠鏡をのぞくと像がひっくり返って見えます。それと同じように人間の目もレンズなので網膜に映る映像はひっくり返っているのです。でも私たちは正しい向きで物がみえます。目の段階では倒立像をみていても、視神経から脳で処理するどこかの段階で元に戻して私たちに正立像を見せているのです。私にはどうしても「目の前のものをそのまま見ている」という感覚しかありません。ただ唯一、車の運転をしているときだけは「現実の画像ではないかも」と思うことがあります。これは車のウィンドウの輪郭がフレームがわりになって絵とか映画のような印象を与えてくれるからなんだと思います。
小学校の頃、長い朝礼のとき校長先生の訓話もそこそこに、私は「いま見ているこの光景は、みんなにも同じように見えているのだろうか?」と考えていました。そんな疑問を持っている子供は私だけではなかったようで、よく友達とそんな議論をしていました(いま気が付きましたが、私が勝手に議論に巻き込んでいた疑惑もあります。私は自分の思ったことを一方的に話してしまう癖がありました)最近読んだ書籍「知能とは何か(田口善弘著)」では、脳のことを現実シミュレーターと解釈しています。目から来た情報を3D映像にシミュレートするというわけです。私も同じように感じていましたし、映画マトリックスや、漫画の「全部夢でした」という夢オチなどを考えると、多くの人が同じ感覚を持っているのではないでしょうか。名作である寄生獣という漫画でも、ラストの方で寄生生物であるミギーが「人間とは脳の構造が全く異なり、まったく違う映像をみている。同じ脳を持つ人間同士でも想像を絶するくらい異なるはず」と指摘しています。みんなそう思っているのです。
今日は、そんなことについて論じてみたいと思います。これはAIの仕組みについて想像したり、人とのコミュニケーションに深みを与えたりする効果を期待できる・・・わけではまったくなくて、単にこういう話が好きなので書いちゃいます。
現実世界を脳内で映像化するには、2つの難しさがあるように思います。3次元表現と色です。
3次元表現
人の脳は、左右の目からくる視差のある画像を使って立体感を得られるような視覚(立体視)を実現しています。立体となる情報は視差以外にもあって、遠くが小さく見える現象や、近くを見る時に遠くがぼやける(もしくはその逆)の焦点深度、近くのものほど細かいものがみえること(解像度)などを活用しています。小学校の頃に読んだ本には「片目をつむると立体的に見えなくなります」と書かれていましたが、実際には片目をつむってもちゃんと立体的に見えます。それは長年の立体視の経験をもとに、これらの情報を学習して立体の情報を得ているからだと思います。
しかしその結果として得られた立体感というのはとても感覚的なものです。自分はあきらかに3次元空間の中に存在していると感じるのですが、それがどうしてそう感じさせるかがわからない。「視覚はよみがえる(スーザン・バリー著)」という本では子供時代に斜視であった著者が、あるとき「自分は立体視をしていない」ことに気が付きます。子供時代に立体視の経験を積んでいなかったため、手術によって斜視が治っても立体視ができず、しかし人と見え方が異なるとは気が付きませんでした。しかし神経生物学者である彼女はその事実に気がつき、訓練を経て、ある日、自分が舞い落ちる雪の中に存在することに気が付きます。その瞬間までは雪は映画のように向こうの方に貼りついが画像だったそうです。その「自分が空間の中に位置している」という感覚は、とても主観的なので、人によって異なる、つまり同じ映像をみていていも、立体視のために脳がしているシミュレーションは、人によって違う可能性は高いように思います。
また立体的構造物を2次元に描写するには、中学校の時に習った一点・二点透視法などを使います。これは遠くのものは小さく見えるという事実を幾何的な方法で実現しています。透視法によって描かれた画像は、目で見る映像と同じです。しかし、浮世絵は遠近法を無視して描かれています。もしかしたら遠近法的見え方は学習によって身につくもので、江戸時代の人は違う見え方をしていたのかも・・・とも思っています。
色の見えかた
色は事情がさらに複雑です。光は波ですので波長を持ちます。波長の違いを認識した方が、温度がわかったり、果実を見つけたりできるので便利だったのでしょう。人間は波長の違いを色として認識します。しかし電磁波である光に物理的に色がついているわけではありません。色は脳による波長表現なのです。
色には不思議な特徴があります。中でも私は混色が最も不思議に感じます。緑の光と赤の光を混ぜると黄色に見えます。例えばパソコンやテレビのディスプレイはこの仕組みを使って黄色を表現しています。しかし緑と赤の混ざった光は、黄色の単色光とは別物です。緑と赤の混ざった光を機械で測定すると緑と赤の波長の光が観測されます。緑は500-570nm、赤は650-780nm程度の波長です。一方で黄色の光は595-650nmの波長の光が測定されます。しかし人間の目には「緑と赤を混ぜた光」と「黄色の光」の区別がつきません。これが同じ波でも音とは違う点です。音の場合はドとミとソを一緒に聞くとドミソという和音が聞こえ、訓練をした人なら「ドとミとソが鳴っている」と音を分解することができます。しかし色の場合は和音に相当するような和色はなく、混ざった色を分解できないのです。ちなみに赤と青の光を混ぜたマゼンタ(赤紫)は単色では存在しません。完全に脳内だけに存在する色なのです。
このようなことが起きる理由は、人の目は色を赤・青・緑の3つの色に反応する視細胞の組み合わせで認識するからです。緑と赤が混じった光を見たときも、黄色の光をみたときも、同じ量だけ緑と赤に反応する視細胞が情報を伝えるので、同じ色に見えるわけです。余談ですが「宇宙には緑色の星がない」ことも実は人間の視覚の問題です。
そう考えると色は脳内で作られているので、色の感じ方は個人差がありそう。そもそも同じ色を同じように見えているかはわかりません。これは私が小学生の頃からの疑問で、人は赤い色を同じ赤として見えているのか、ずっと考えていました。薄い赤、濃い赤という程度の違いではなく、全く異なる色として見えているかもしれないからです。色を言葉で表現する方法はないので、答えはわからないままです。
しかし色の見え方は人によって違っているのでは?と思わせる事実もあります。たとえば日本人は青は男性色、赤は女性色として感じます。マレーシアに行った時のこと。私は間違えて女子トイレに入りそうになりました。なぜなら男子トイレが赤、女子トイレが黒で表示されていたからです。男女に逆の色をあてていることで、もしかしたらまったく違う色に見えているのかも、とも思いました。でも、そうではなくて、単にこれは文化的な背景なのかもしれません。
また明らかに異なる色が見えている例もあります。淡い色彩を基調とする印象派の代表画家モネは、晩年は原色の赤色などを使った鮮烈な色彩の絵を描いています。これはモネが視覚、とくに色彩感覚を晩年に失っていったからと言われています。モネ好きの私ですが晩年の作品は苦手でした。しかし上野の美術館で初めて晩年の作品をみたとき、その躍動する生命感に感動しました。自分の命が間も無く尽きようとしているとき、これほどの生命感を出すことができるのです。
3次元と色の2つを考えるだけでも、人によって見えている光景が全く異なる可能性を理解ことができます・・・とここまで自分の好きな話にお付き合いいただきました。でも、人によって見え方全く異なる可能性を認識するだけでも、多様なものの見方をするためのヒントになるかもしれない、とも思っています。
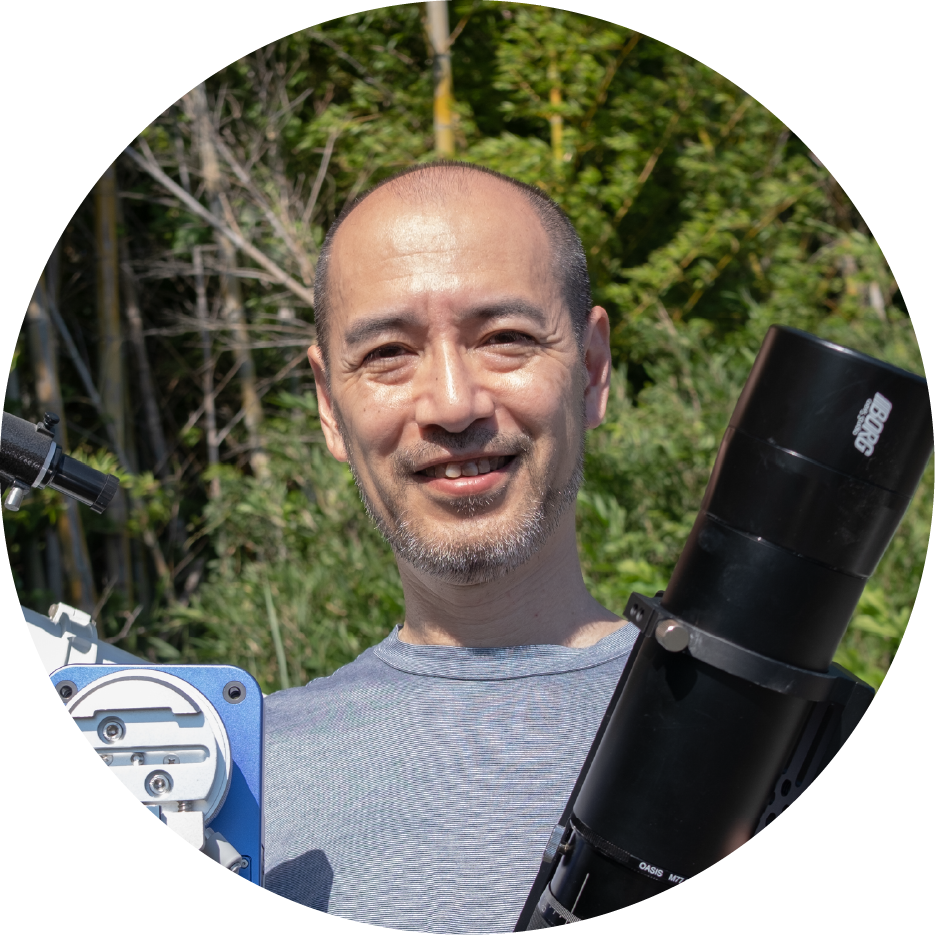
2026年2月16日
アストロライフ合同会社 代表
丹羽雅彦